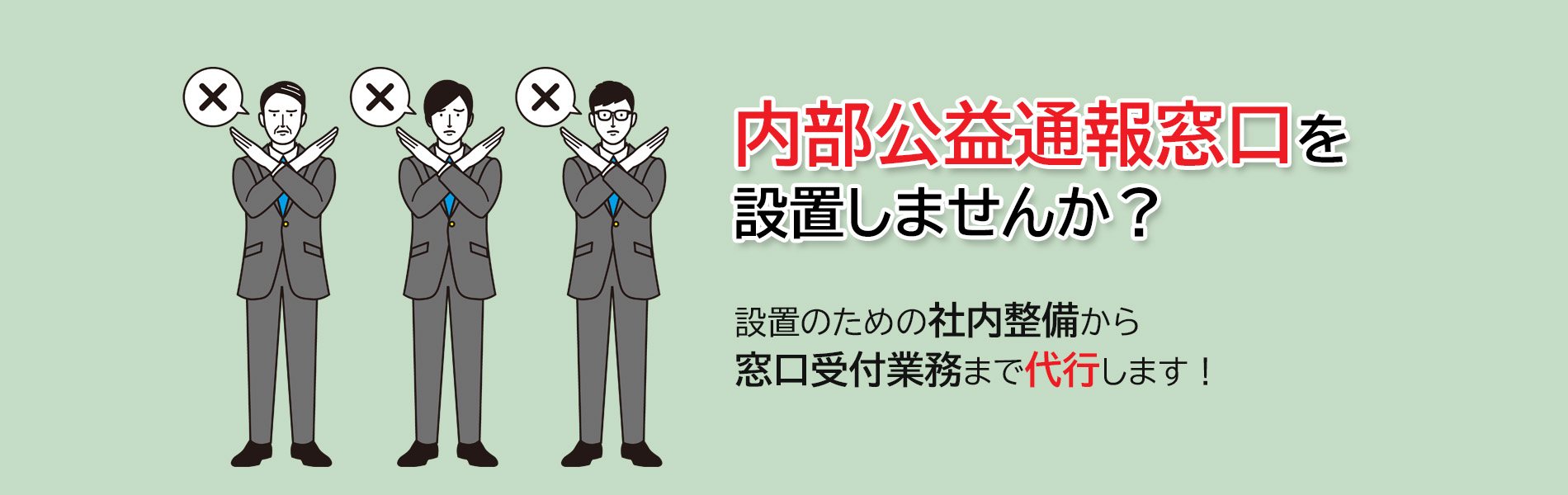内部公益通報窓口は、自社内の不正行為(横領、ハラスメントその他法令違反行為)の存在にいち早く気づき、問題が大きくなる前に対処するための手段として、非常に有効な方法です。
また、内部公益通報窓口は、自社の問題や不祥事が、いきなり監督官庁や取引先会社、インターネットやマスコミに通報されるのを防ぎ、自社内で問題を処理、完結させるための受け皿としても機能します。
コンプライアンスが重視され、たった一つの問題事案が、経営に深刻な影響を与えかねない時代です。
会社を守るため、内部公益通報窓口を設置しましょう。
※常時使用する労働者の数が301人以上の事業者は、内部公益通報受付窓口の設置が、法律上義務付けられています(公益通報者保護法第11条第2項)。
※パートタイマー、契約社員等も、臨時的に雇い入れられた場合でなければ、常時使用する労働者に含まれます。
※派遣労働者は、派遣先及び派遣元の双方において、常時使用する労働者に含まれます。
※常時使用する労働者の数が300人以下の事業者は、努力義務ですが、設置をおすすめします。
-
内部公益通報窓口は自社で設置してもよいですか?
-
内部公益通報窓口は自社で設置することもできます。
しかし、従業員から見ると、自社内の公益通報窓口に通報することをためらうケースも考えられ、受け皿としての役割を果たせない可能性があります。
また、公益通報者保護法やそのガイドラインに則って、適切に通報窓口を設置、運営するためには、法的知識が必要です。
会社にとって負担が大きいため、外部機関に依頼することをおすすめします。
-
内部公益通報窓口は顧問弁護士に依頼すればよいですか?
-
顧問弁護士に内部公益通報窓口も併せて委託するケースは多いです。
しかし、顧問弁護士が、通報者を相手方とする事件を受任することができなくなるというデメリットがあることは、あまり知られていません。
例えば、顧問弁護士がハラスメントの通報を一度受けてしまった場合、その顧問弁護士は、そのハラスメントの事案について、会社からの法律相談に応じることができなくなり、代理人として活動することもできなくなります。
利益相反の観点から、弁護士法上禁止されているからです。
そうなってしまっては、頼む弁護士がいなくなってしまい、会社は困ってしまいます。
そのような事態を防ぐため、顧問弁護士と内部公益通報受付窓口を委託する弁護士を予め分けることも良いと思います。
-
内部公益通報窓口の設置の仕方が分かりませんが、教えてくれますか?
また、その料金はいくらですか? -
内部公益通報窓口の設置をするためには、いろいろな社内整備をする必要があります。
そのためには、公益通報者保護法やそのガイドラインに関する知識が必要です。当事務所は、これらについて、すべて無料でサポートさせていただきます。
① 内部通報規程の作成、整備
② 内部公益通報対応業務に従事する者(従事者)の指定
③ 従事者の研修
④ 従事者から誓約書を徴求
⑤ 内部公益通報窓口のポスターの掲示※内部公益通報窓口の受付業務の月額契約をご依頼いただく場合に限ります。
※同月額契約が途中解約となった場合は除きます。
-
内部公益通報窓口受付業務を依頼した場合、どこまでやってくれますか?
また、その料金はいくらですか? -
業務の範囲は、以下のとおりです。
① 通報の受付
② 通報者からの事情聴取
③ 貴社へ通報内容の報告
④ 通報者へ途中経過の報告(適宜)
⑤ 通報者へ調査結果の報告料金は月額3万円(税別)です。
上記の業務の範囲を超えて、通報内容に関する事実調査等をご依頼いただく場合は、別途料金が必要となります。